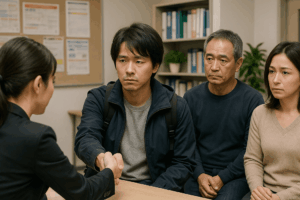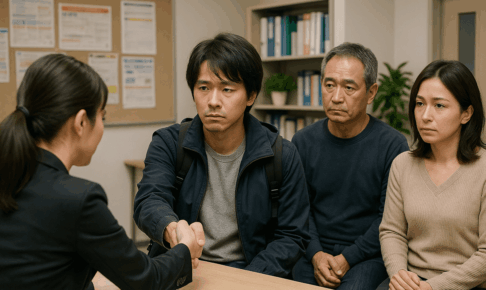「図書館で働きたい。」そんな思いを抱いたときに浮かぶ職業のひとつが「司書(ししょ)」です。
司書とは、図書館で働く専門職の人のことであり、主に図書館の資料(本、雑誌、CD、DVD、電子資料など)の収集、整理、保存、提供、情報案内など、図書館運営全般に関わる様々な業務を行います。
中でも、公的機関に所属する「公務員司書」は、安定した働き方と地域貢献性の高さから、一定の層に人気があります。
このページでは、公務員司書の仕事内容や勤務先、年収や公務員司書になるための方法を詳しく説明していきます。
※「公務in」で、「司書の公務員採用試験日程・求人情報」をチェックしよう!
公務員司書とは?民間の司書との違い

以下では、公務員司書とは?から、民間の司書との違いを詳しく説明していきます。
公務員司書とは?
公務員司書とは、図書館業務の専門性を活かしながら、地域住民や学生など多様な利用者に対して情報サービスを提供する公共職です。
民間の司書とは異なり、自治体や教育委員会などの公的機関に所属し、地方公務員としての立場から、図書館の運営や読書活動の推進、行政と連携した事業にも関わります。
公務員司書と民間の司書との違い
民間の司書と公務員司書との違いとは、具体的に何でしょうか。
公務員司書は、主に公立図書館(市町村立、都道府県立など)や国立大学図書館に勤務し、公務員として安定した身分と給与体系を持ちます。地域住民への幅広いサービス提供が主な業務で、異動により多様な経験を積むこともあります。
一方、民間の司書は、私立大学図書館、専門図書館、企業内の資料室、または公立図書館の運営を受託する民間企業などで働きます。雇用形態は多様で、給与や待遇は所属機関によって異なり、特定の専門分野に特化した業務が多い傾向にあります。安定性は公務員に劣る場合もありますが、特定の専門性を追求しやすい点が特徴です。
具体的には、以下のような違いがあります。
| 項目 | 民間の司書 | 公務員司書 |
|---|---|---|
| 所属先 | 私立大学図書館、専門図書館、企業の資料室、NPO運営図書館、図書館業務受託会社など | 公立図書館(市町村立、都道府県立)、国立国会図書館、国立大学図書館など |
| 雇用形態(身分) | 正社員、契約社員、派遣社員、パート・アルバイトなど | 基本「正職員」の地方公務員、国家公務員 |
| 採用方法 | 各機関の採用試験 | 公務員採用試験 |
| 給与・待遇 | 各機関の規定による(比較的幅広い) | 公務員の給与体系に基づく(安定性が高い) |
| 安定性 | 比較的低い場合もある(契約更新、経営状況による) | 比較的高い(終身雇用、福利厚生が充実) |
| 異動 | 所属機関内での異動は限定的。部署異動はあり得る。 | 同一自治体内の他部署への異動、他図書館への異動、または国家公務員の場合は各省庁の資料室などへの異動の可能性も |
| 業務内容 | 所属機関の特性に応じた専門性(例: 大学図書館は学術研究支援、企業資料室は社内情報管理) | 地域住民への幅広いサービス提供、行政資料の管理、企画・広報活動など。幅広い分野に対応。 |
| キャリアパス | 所属機関内での昇進、他機関への転職、専門分野の深化 | 昇任、管理職への道、他部署への異動によるキャリアチェンジも可能 |
公務員司書は、基本的に地方公務員が多く、国立国会図書館などの採用試験が行われることは少ないと言えるでしょう。
公務員司書の主な勤務先
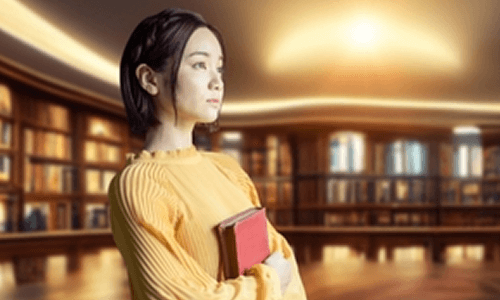
公務員司書が活躍する場は、市区町村の図書館だけにとどまりません。都道府県立図書館や教育委員会、さらには学校や専門機関など、配属先は多岐にわたります。
勤務先によって求められる専門性や業務内容は異なり、それぞれの現場で地域社会や教育現場を支える重要な役割を担っています。ここでは、公務員司書の主な勤務先について、代表的な3つのケースに分けて詳しくご紹介します。
市区町村立図書館
もっとも多くの公務員司書が勤務しているのが、市区町村が設置・運営する公共図書館です。
これらの図書館は、地域住民が自由に本を借りたり、調べものをしたり、イベントに参加したりできる「生活に身近な知の拠点」として機能しています。
市区町村立図書館の司書は、資料の選定や分類、貸出管理といった基本的な図書館業務に加えて、子ども向けの読み聞かせイベント、高齢者や障がい者向けのバリアフリーサービス、地元の歴史に関する郷土資料の展示など、多岐にわたるサービスを展開しています。
また、自治体の施策に沿って読書活動の推進や情報格差の是正を目指した取り組みにも積極的に関わります。
さらに、住民からのレファレンス(調べもの)依頼にも対応し、地域の学びや生活の質の向上を図る役割も担います。近年ではICTを活用したデジタル図書館の導入や、SNSを活用した情報発信にも力を入れており、地域に根ざした柔軟なサービスが求められています。
都道府県立図書館や教育委員会など広域的な職場
都道府県立図書館は、市町村の図書館を支援しながら、より広域的で高度な情報提供を行う拠点です。公務員司書としてここに配属された場合、専門性の高い業務を任されることが多く、調査研究の支援や、行政文書・古文書・学術資料の整備など、資料の高度利用に対応する力が求められます。
また、都道府県の教育委員会に所属する場合、主な業務は学校図書館の運営支援や、各学校に配置される司書教諭・学校司書との連携による読書教育の推進です。読書感想文コンクールの開催や読書週間の企画、図書館間連携の調整など、教育政策に沿った業務を遂行することが求められます。
こうした広域的な勤務先では、現場での直接的なサービス提供だけでなく、制度設計や研修企画、他館とのネットワーク構築など、図書館全体の発展を見据えたマネジメント的な業務も期待されることが多い点が特徴です。
学校図書館や専門機関
一部の自治体では、公務員司書が直接学校図書館に勤務する場合もあります。小中学校や高等学校に配置される司書は、児童・生徒の読書活動支援や学習支援を主な業務とし、授業と連携した資料提供や調べ学習の指導、図書館利用のルール教育など、教育現場に密着した職務を担当します。
また、大学附属図書館や行政機関に併設された専門図書館など、より専門性の高いフィールドに勤務する場合もあります。たとえば、法務関連の行政機関では法令資料の整備や情報検索支援、産業振興センターではビジネス支援資料の提供など、それぞれの分野に特化した情報サービスを提供します。
このような専門的な勤務先では、一般的な図書館業務に加え、利用者の専門的なニーズに的確に応えるための知識やスキルが必要とされるほか、チームでの協働や各種研修への参加など、継続的な学習と自己研鑽が求められる環境でもあります。
公務員司書の仕事内容

公務員司書は、図書館運営の中核を担う専門職として、日々多岐にわたる業務を行っています。その仕事内容は単に本の貸し出しにとどまらず、資料の選定・管理から、利用者対応、地域への情報提供活動まで幅広く、図書館という公共施設の質を左右する重要な業務ばかりです。
以下では、公務員司書の主な業務内容を3つの側面から詳しく説明します。
図書館資料の整備
図書館の基盤ともいえる資料整備は、公務員司書の中核的な仕事のひとつです。新たに購入する本や雑誌、視聴覚資料などを選定し、分類・登録作業を通じて図書館の蔵書として整備していきます。選定にあたっては、地域のニーズや読者層、自治体の予算などを考慮する必要があり、単なる“本好き”だけでは務まらないバランス感覚が求められます。
また、資料は日本十進分類法(NDC)などのルールに従って分類され、図書館システムにデータとして登録されます。古い資料の修理・保存や、不要資料の除籍、廃棄処理も司書の重要な仕事です。
貸出、返却、レファレンス対応などの利用者サービス業務
来館者へのサービス提供も、公務員司書の欠かせない業務です。カウンターでの貸出・返却対応はもちろん、館内利用案内、資料の場所案内、予約・リクエストの受付など、利用者一人ひとりのニーズに応える柔軟な対応が求められます。
また、利用者が調べものをしたいときに支援する「レファレンスサービス」も司書の専門性が発揮される場面です。調査テーマに応じて、最適な資料や情報源を提案したり、複数の情報を組み合わせて提示したりと、単なる検索作業以上のスキルが必要です。
加えて、視覚障がい者への音訳資料の案内や、子ども・高齢者へのサービスなど、多様な利用者層に対応した接遇力も重要です。
図書館イベント・展示・広報などの企画運営
図書館は「静かに本を読む場所」から、地域とつながる「情報と文化の拠点」へと役割を広げつつあります。公務員司書はその流れに沿って、さまざまなイベントや展示、広報活動を企画・実施します。
具体的には、絵本の読み聞かせ会、読書感想文講座、地元資料の特別展示、地域の学校や団体との連携事業などがあります。
これらの活動には、企画立案から資料選定、ポスター作成、司会進行、報告書作成まで一貫して関わるため、図書館外の人々との連携力や調整力も問われます。近年ではSNSやホームページを活用した図書館広報も重要になっており、Webリテラシーや発信力が活かせる分野でもあります。
公務員司書の年収はどれくらい?
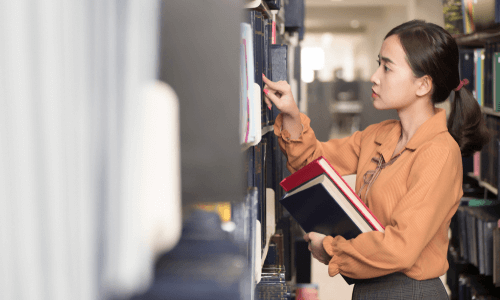
公務員司書の年収は自治体によって多少異なりますが、初任給は概ね月額19万〜23万円程度で、「年収約360万~420万円+各種手当」が一般的です。勤続年数や昇給に伴い、年収は着実に上昇していきます。
以下は、埼玉県庁における公務員司書の年収例です。(令和7年4月1日時点)
| 初任給(地域手当込み) | 約228,100円 |
|---|---|
| 1年目の年収 | 約376万円 |
| 5年目の年収 | 約425万円 |
※1年目の年収(概算):228,100円 × 12ヶ月 + 228,100円 × 4.5ヶ月(期末・勤勉手当) ≒ 3,763,650円
※5年目の年収(概算):262,400円 × 12ヶ月 + 262,400円 × 4.2ヶ月 ≒ 4,250,700円
また、正規職員として長期勤務することで退職金制度の恩恵も受けられ、60歳時点での退職金額は1,000万円前後となることも珍しくありません。
さらに、公務員司書は雇用が安定しており、各種手当や福利厚生も充実しています。結婚・出産・育児・介護など、ライフイベントと両立しやすい環境が整っている点も大きな特長です。特に女性職員にとっては、出産・育児休業や復職支援制度の整備が大きな魅力となります。
このように、公務員司書は初任給こそ控えめですが、昇給制度・福利厚生・退職金を含めたトータルの待遇が非常に手厚く、将来的に安定した生活を築きやすい職種といえるでしょう。
公務員司書になるには?
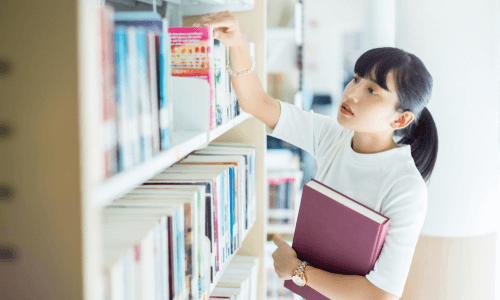
公務員司書になるためには、司書の資格を取得(または取得見込み)したうえで、各自治体などが実施する公務員試験に合格する必要があります。
以下では、公務員司書に必要な資格、試験制度の仕組み、さらに実際の求人情報の探し方までを詳しく解説します。
必要な資格と取得方法
公務員司書として採用されるには、「司書資格」を有していること、または取得見込みであることが大前提です。
司書資格は、文部科学省が定める課程を履修することで取得でき、主に大学・短期大学・専門学校で取得可能です。なお、社会人から中途採用で公務員司書を目指す場合も、まずは司書資格を取得しておくことが必要です。
公務員試験を受けるための条件・募集資格
公務員試験を受験するための条件や募集資格は、各自治体などによって異なります。以下は一般的な傾向としてよく見られる条件です。あくまで目安として参考にしてください。
| 必要な資格 | 司書の資格、又は資格取得見込み |
|---|---|
| 年齢 | 一般の公務員試験の場合は30歳未満までの場合が多い ※ただし、社会人枠などの場合は、40歳未満までの場合が多い |
| 学歴 | 4年制の大学卒以上が多く、2年制の短大(2年制の専門学校含む)以上の学齢制限が多い |
| 国籍 | 日本国籍が基本だが、自治体によっては国籍不問の場合もあり |
また注意点として、「社会人枠」や「経験者枠」など、特別枠が設けられている場合には、原則として中途採用を対象とした募集であり、司書としての実務経験が数年以上求められるケースが多く見られます。
司書の公務員試験・求人情報を探す
司書の採用試験における倍率は自治体によって異なりますが、全国的に非常に人気の高い職種であり、競争は激しい傾向にあります。
また、司書は離職率が低く、募集自体が限られているため、採用試験の実施数も多くはありません。そのため、公務員の採用試験情報に特化したサイト「公務in」で、「司書の公務員採用試験日程・求人情報」を随時チェックしておくことをおすすめします。
希望する地域の募集が出るまで、こまめに情報を探しましょう。また、働きたい図書館や市区町村がある場合は、事前に目星をつけておき、各自治体の公式サイトも定期的に確認しておくと良いでしょう。
公務員試験の内容について
公務員司書になるための試験内容は、各自治体などによって異なります。
ただし、一般的には司書枠での募集は「上級(大卒程度)」で行われることが多く見られます。ここでいう「大卒程度」とは、大学卒業の有無ではなく、大学卒業相当の学力を求める区分を指します。
各自治体によって実施される試験の組み合わせはさまざまですが、以下のようなパターンがよく見られます。
- 教養試験 + 面接試験
- 教養試験 + 専門試験 + 面接試験
- 教養試験 + 性格・事務適性検査 + 面接試験
- SPI試験 (+ 専門試験)+ 面接試験
教養試験では、国語、数学、英語、社会、自然科学などの基礎科目に加えて、時事問題や論作文が課される場合もあります。特に論作文では、図書館行政や図書館業務に関するテーマが出題されることもあります。
試験対策としては、過去問演習や論作文対策、そして面接練習などを計画的に進めることが重要です。
まとめ
公務員司書は、単なる図書館業務にとどまらず、地域社会や教育現場に貢献する「公共の情報専門職」として、多面的な役割を担う重要な職種です。市区町村の図書館から都道府県の広域機関、さらには学校や専門図書館に至るまで、活躍の場は幅広く、その分野で求められる知識やスキルも多岐にわたります。
公務員司書になるためには、司書資格の取得に加え、地方公務員試験に合格する必要があります。自治体によって試験制度や採用状況が異なるため、早めの情報収集と計画的な対策が合格へのカギとなります。特に採用人数が限られるため、しっかりと準備を進めておくことが大切です。
図書館という空間を通じて、すべての人の学びと成長を支える仕事に興味がある方にとって、公務員司書は非常にやりがいのある職種です。
情報の選別・提供だけでなく、地域文化や教育、公共サービスの一端を担いたいと考える方は、ぜひこの道を目指してみてはいかがでしょうか。