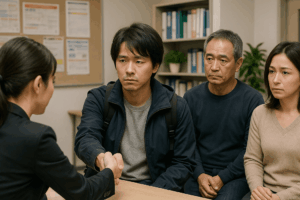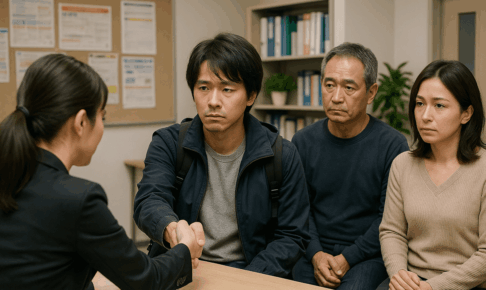自治体採用で「内定辞退率が5割」に達するケースが相次いでいます。これまで誇張的に語られることもありましたが、現在は現場で実際に起きている深刻な現象です。背景には、賃上げで勢いづく民間企業、複数試験の併願が当たり前になった採用環境、そして「公務員として働く魅力」を十分に伝えきれていない現状があります。
コロナ禍後の人手不足と賃上げの流れを受け、就職市場は完全に売り手優位となりました。初任給や地域手当、昇給のスピード、柔軟な働き方などで民間が優位に立つ一方、自治体は採用広報の接点が限られ、最終的な意思決定の段階で「待遇」「勤務地」「成長の実感」で逆転される状況が広がっています。
日本経済新聞は「内定辞退が半数を超える自治体が相次ぐ」と報じています。地域や職種を問わず、選考の終盤で辞退が連鎖的に発生することが課題として浮き彫りになっているのです。
現状では、東京都日野市の新卒事務職で62.5%が辞退しました。北海道では帯広市が54.8%、函館市が52%に達しています。小樽市も前年に51.1%と報じられ、道内主要都市の多くで2割以上の辞退が確認されています。テレビやウェブの報道もこの傾向を裏付けており、「安定の公務員」というブランドだけでは志望者を引き止められない現実が明白になっています。
| 自治体 | 区分 | 内定辞退率・状況 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 東京都日野市 | 新卒事務 | 62.5%(合格24人中15人が辞退) | ABEMA TIMES |
| 北海道帯広市 | 大卒区分 | 54.8%(過去最高) | 十勝毎日新聞 |
| 北海道函館市 | 大卒一般事務 | 52%(過去10年で最高) | 北海道新聞 |
| 北海道(道内傾向) | 主要都市 | 9市で2割以上、帯広・函館は5割超 | 北海道新聞 |
| 小樽市 | 24年春採用 | 51.1% | 北海道新聞 |
内定辞退の影響は採用数の不足だけにとどまりません。配属現場での欠員や応援体制の慢性化、若手育成の遅れ、住民サービスの遅延など、さまざまな「静かなコスト」を生み出しています。再募集や再面接、再オンボーディングは年単位で非効率をもたらし、採用担当者の疲弊も深刻です。さらに「辞退が多い組織」という評判が翌年度以降の志願者数を減らし、悪循環に陥りやすい点も課題です。
では、なぜ辞退が起きるのでしょうか。要因は大きく四つに整理できます。第一に報酬の差です。初任給や地域手当、住宅補助、賞与を合算すると、民間が上回るケースが増えています。第二に選考のタイミングです。民間の内定が早く確定する一方で、自治体の合否通知は遅れがちで、受験者が待ちきれず辞退することにつながります。第三に情報不足です。仕事内容や成長機会、異動や評価の仕組みが十分に伝わらず、最後は不安から辞退に至ります。第四に勤務地や通勤の負担です。都市圏では選択肢が多く、近隣自治体や特別区、都庁に人材が流出しやすい傾向があります。
一方で、打開策を講じる自治体も出てきています。大阪府和泉市は「初任給日本一」を掲げて応募が急増し、倍率が大幅に上昇しました。日野市や多摩市、稲城市は合同説明会を実施し、地域全体の魅力を伝える取り組みを行いました。一次から最終試験までを短縮し、職員によるトークや体験型選考を導入した自治体もあります。内定後にオファー面談を行い、住居手当や副業の可否まで具体的に確認することで辞退を防ぐ動きも広がっています。
辞退防止のための実践例としては、合格発表を前倒しして仮内々定を明確にすること、内定後30日間のフォロー体制を設計すること、初任給や手当を民間比較レンジ付きで提示すること、初任期の研修や評価を一枚の資料にまとめて可視化すること、近隣自治体と連携して説明会や試験日程を共同設計すること、さらに仕事の意義を具体的なエピソードで伝えることなどが挙げられます。
和泉市の事例では、人事給与制度の改革により初任給を段階的に引き上げ、採用特設サイトやメディア露出と相乗効果を生み出しました。その結果、応募数が集中的に増加しました。待遇の見直しと若手職員の声を前面に出す広報が、最後の一押しとなったとみられます。
編集部からのコメント
「自治体の内定辞退5割」は一過性の問題ではありません。重要なのは待遇競争だけに陥らず、志望者が“働く意味”を実感できる仕組みを整えることです。給与や手当といった数字と、住民サービスの成果という物語を両立させ、意思決定の“最後の一押し”を取りに行くことが、2025年の自治体採用で勝ち残るための条件といえます。