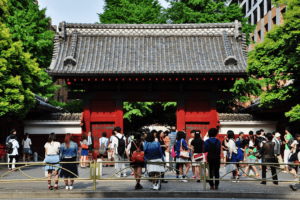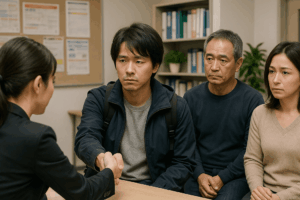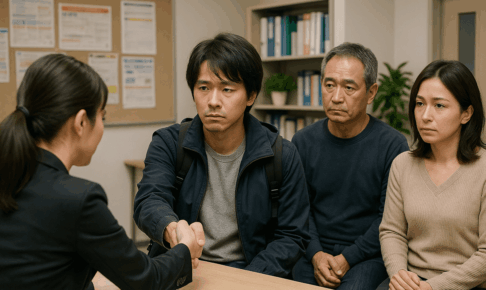人事院はこれまで年1回だった総合職試験(大卒程度・教養区分)を、2027年度から年2回へと拡充すると2025年6月に発表しました。
さらに受験資格を大学2年修了者まで広げることで、より早い段階から国家公務員を志す学生の挑戦を後押しする狙いがあります。
以下では、制度改正の背景や意義、そして地方自治体に及ぶ影響について整理しました。
背景として、国家公務員試験の志願者数は近年減少が続き、優秀な学生の多くが民間企業へ流れる現象が課題となってきました。人事院は人材確保の裾野を広げるため、早期に受験機会を提供する方針を示し、国家公務員の魅力を若い段階で体感してもらうことを重視しています。
大学2年からの受験解禁は、学生にとって「腕試し」としての挑戦を可能にし、将来の選択肢を広げる契機になると期待されています。
これまでの試験は年1回で大学3年程度が対象でしたが、今後は年2回に増えることでチャンスが倍増します。さらに学部2年生からの受験が可能になることで、就職活動を控える前に経験を積めるのが大きな利点です。
試験を早期に経験することで、公務員に向いているかどうかを見極められるという実践的な意味合いも大きいでしょう。
一方で、この改革は地方自治体の採用活動にも少なからず影響を与えると見られています。
地方上級試験や特別区試験と受験時期が重なる可能性があり、学生の試験スケジュールに調整が必要になるかもしれません。また、国家公務員試験の機会が増えることで、優秀層の一部が国家公務員志望へ流れる懸念もあります。
ただし、全体的な受験者数の増加によって、公務員志望者全体の母集団が広がる効果も見込めるため、自治体にとっても潜在的にはプラス要素となり得ます。
学生側にとっては、大学2年からの受験挑戦がキャリア形成の新しい出発点になります。これにより、大学のキャリアセンターも講座や模擬試験などを1年早めに提供する必要性が高まりそうです。
また、地方自治体は人材の流出を防ぐため、国家公務員との違いや地元で働く魅力を積極的に発信することが求められます。例えば、地域に密着した行政のやりがいや、生活との両立のしやすさなど、国家公務員では得にくい価値を明確に伝える工夫が必要となるでしょう。
この改革は単に試験回数を増やすにとどまらず、公務員人材市場全体に大きな変化をもたらす可能性があります。国家と地方、それぞれの立場で「人材確保競争」が加速する一方で、公務員という職業の裾野が広がり、多様な学生が挑戦する機会を得ることは社会にとっても意義深いことです。
今後の運用次第では、国家と自治体の間での人材の流動性が高まり、公務員採用のあり方そのものを変える契機となるかもしれません。
編集部からのコメント
今回の制度変更は、学生にとって受験のハードルを下げ、未来への可能性を広げる一歩といえます。一方で地方自治体にとっては人材確保の競争が厳しくなる局面も考えられます。
重要なのは、この変化を脅威と捉えるのではなく、新たな採用戦略を構築する好機とする視点です。国家と地方がそれぞれの魅力を発信し合うことで、公務員全体の存在感や魅力が高まり、結果として学生にとって選択肢が増えることにつながるでしょう。
参照元:人事院|報道発表資料