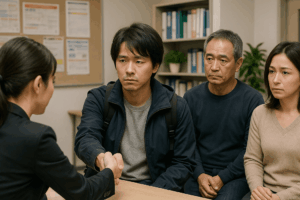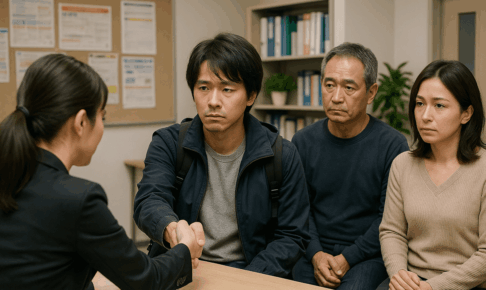このページでは、「みなし公務員(準公務員)とは」についての詳細と、みなし公務員として働く一般的なメリット・デメリットについて説明していきます。
みなし公務員とは?

みなし公務員とは、国または自治体の職員ではありませんが、公益性・公共性が強い仕事となり、公務員とみなされる職務に従事している人(法令により公務に従事する職員とみなされる者)を指します。
公務員と働き方が似ている点や守秘義務がある点、役割が似ている点、事業の安定性がある点より、働く職員は公務員と似たような扱いや待遇を受けることが可能です。
しかし、刑法の適用は公務員と同じ扱を受け、罰則についても刑法が適用されます。
また、みなし公務員のことを「準公務員」と呼ぶ場合もあります。
みなし公務員のエビレンス
総務省総務省
みなし公務員とは、公務員ではないが当該法人の設立根拠法において、「刑法、その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす」旨の規定(みなし公務員規定)を持ち、罰則について刑法が適用されるものをいう。
みなし公務員と類似のものとして、みなし公務員規定を持たないが、その設立根拠法に収賄等についての罰則規定を持つ法人がある(例:日本たばこ産業、NTT 東日本、JR 北海道等)が、これら法人に係る罰則の適用は、それぞれの設立根拠法の規定が適用されるものであり、刑法の規定が適用されるものではない。したがって、これら法人は、みなし公務員に該当しない。
第二十条 機構の役員及び職員(以下「役職員」という。)は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
引用:総務省
一般財団法人 行政管理研究センター
みなし公務員とは、公務員ではないが当該法人の設立根拠法において、「刑法、その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす」旨の規定(みなし公務員規定)を持ち、罰則について刑法が適用されるものをいう。
引用:一般財団法人 行政管理研究センター
みなし公務員の一例
以下は、みなし公務員となる一例となります。
- 日本年金機構の役員及び職員の地位
(日本年金機構法第20条) - 独立行政法人国立病院機構の各施設に勤務する職員
(独立行政法人国立病院機構法第14条) - 国立大学法人の職員
(国立大学法人法第19条) - 日本銀行の役職員
(日本銀行法第30条) - 日本郵便株式会社の従業員
(郵便法第74条)
また、特別法で国による一定の権限が付与されている特殊会社、特殊法人、公営競技などは、各々の法律で「公務に従事する職員とみなす」という記述がありませんが、公務員と同様に公益性・公共性が高いものであるため「みなし公務員」として表現されることもあります。
(例)特殊会社、特殊法人、公営競技:高速道路系の職員、日本電信電話(NTT)、日本たばこ産業、日本放送協会、日本中央競馬会、東京地下鉄など
参照:Wikipedia
みなし公務員の刑法の適用について
先ほど説明したように、「みなし公務員」は公務員と同じ刑法の適用を受け、罰則についても刑法が適用されるため、以下の内容が適用されます。
- 秘密の保持義務(守秘義務)
- 公正妥当な執行を担保するための贈収賄罪
- 公務員職権濫用罪等の汚職の罪
- 虚偽公文書作成罪
- 公務執行妨害罪等
そのため、違反により懲戒処分を受けることや、厳しいもので懲役1年の実刑、又は50万円以下の罰金が課せられる場合もあります。
しかし、国家公務員や地方公務員と違い、争議行為等の禁止(ストライキ等)や兼業(副業等)の禁止等は、包括的に課されることはありません(※1)。
※1:みなし公務員 規定
いわゆる「みなし公務員」規定は、公共サービスの実施に従事する公務員以外の者を刑法上の公務員とみなすことを定めるもので、この規定によって、これらの者に関しても刑法の贈収賄の罪や公務執行妨害罪等を適用することが可能となり、適正な業務の運営に資するものである。
「みなし公務員」規定は、公務員法の規定により公務員に課されている義務を課すものではないことから、これがあっても、これらの者に対して公務員法上の信用失墜行為の禁止、政治的行為の制限といった規定や労働基本権の制約が適用されることにはならない。
引用:内閣官房行政改革推進本部事務局
みなし公務員は副業や兼業が可能?
上記で説明した「みなし公務員の刑法の適用」において、「兼業(副業等)の禁止等は、包括的に課されることはない」とのことで、みなし公務員は副業や兼業が可能のように思われますが、みなし公務員として所属する組織や団体の規定により、多くが副業・兼業を禁止している場合が多いと言えます。
例えば、日本銀行の職員や郵便認証司などが該当します。
(一般企業で、就業規則や規定で禁止されている企業も、禁止されていない企業もあることと同じですが、刑法の適用があるため、強めに禁止されているイメージとなります。)
そのため、実際には「みなし公務員」として副業や兼業を行うことは難しいと言えるでしょう。
みなし公務員であるメリット・デメリット
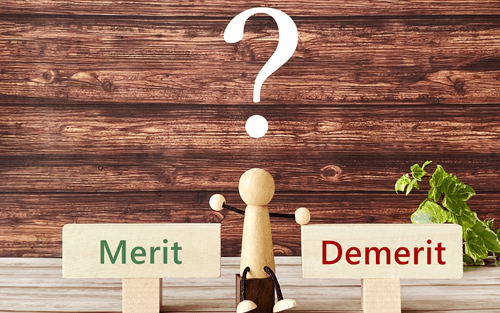
一般企業の社員と比較して、みなし公務員である一般的なメリット・デメリットを説明していきます。
働く待遇や福利厚生が安定している
みなし公務員は、公益性・公共性が強い仕事(国民が必要としている仕事)に従事している場合が多く、働く職員の待遇や福利厚生が安定していることが最大のメリットです。
安定とは、景気に左右されず、勤務先が倒産するようなことが無いことを指しています。
また、産休や育休などの福利厚生も整っていることから、女性が働きやすい職場も多いと言えます。
そのため、給料などを比較すると一般企業に劣る場合もありますが、安定性と言う面では、メリットと言えるでしょう。
退職金の支給がほとんどある
一般企業の場合、退職金を支給しない企業も増えていますが、みなし公務員の場合は各職場の規定により退職金の支給がほとんどです。
また、退職金の割合も各職場の規定により細かく決まっているため、一定水準の退職金を得ることが可能です。
公務員に近しい社会的信用が得られる
みなし公務員が勤務する職場は、名前を聞いたことがある職場も多く、安定性が高いがゆえに、働く職員は社会的信用が得られることがメリットと言えます。
特に、収入が高い場合などは、住宅ローン等の各種ローンが通りやすく、カードの審査なども落ちることは少ないでしょう。
給料表・昇給や昇格の条件等が決まっている
みなし公務員は、各職場の規定により、給料表・昇給や昇格の条件が決まっている場合が多いと言えます。
また、以前は国家公務員や地方公務員職であった場合など(独立行政法人等)は、その条件をそのまま、又は近い形で準用している場合も多いです。
そのため、給料が一定水準で安定していることがメリットと言えるでしょう。ただし、各職場の規定による給料が低い場合はデメリットとなるでしょう。
副業やダブルワークなどが難しい
みなし公務員は、各職場の規定により兼業や副業が禁止されている場合がほとんどであり、時代によってはデメリットとなります。
そのため、公務員と同様の不動産投資や社会的貢献活動等などしか行うことが出来ません。
みなし公務員の規定に縛られる
みなし公務員は、各職場の規定により、守秘義務、接待や贈答の禁止などがあり、規定に縛られてしまうことがデメリットと言えます。
例えば、取引先への手土産や、食事会での先方の食事代の負担、支払ってもらった場合なども贈収賄と判断されます。
まとめ
みなし公務員のメリットは、働く職員の福利厚生や待遇、給料などが安定している点や、社会的信用が得られることだと言え、一方、副業の禁止や公務員に近しい規定に縛られることがデメリットとなるでしょう。
国または自治体の職員ではありませんが、公益性・公共性が強い仕事となるため、やりがいを感じながら働く職員も多く、是非、一度みなし公務員も検討してみましょう。